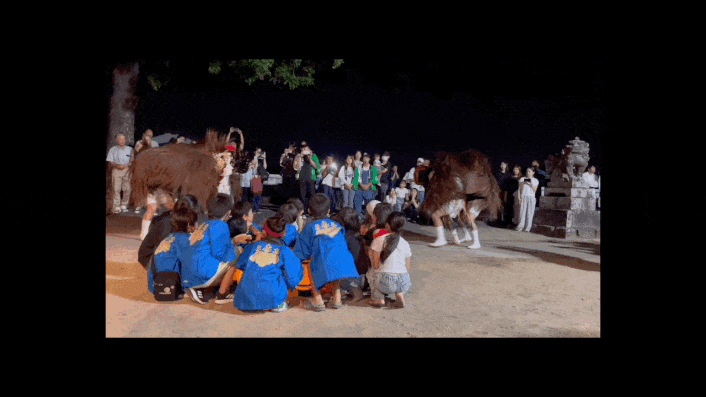📮KURUME LETTER

学生が久留米市指定無形民俗文化財「柳瀬おくんち獅子舞」に参加
10月12日、経済学部の藤谷ゼミの学生と「地域創造特講(伝統文化と地域社会)」の受講生が、久留米市指定無形民俗文化財である「柳瀬(やなせ)おくんち獅子舞」に参加・見学し、地域の伝統文化と継承の現状について学びました。


「柳瀬おくんち獅子舞」とは
「柳瀬おくんち獅子舞」は、筑後川中流域に伝わる珍しい棕櫚(しゅろ)の毛の胴体を持つ二頭獅子舞で、楽器を使わず、二頭が息を合わせて踊るのが特徴です。社伝によると承元2年(1208年)創立の柳瀬玉垂命神社で、旧暦9月9日の重陽の節句に合わせて無病息災・家内安全を祈り邪鬼を祓う「おくんち」として行われてきました。
この獅子舞は久留米市指定の無形民俗文化財であるとともに、『筑後川遺産』にも登録されている貴重な歴史遺産です。


継承の現場を体験
今回の参加では、17名の学生が地区の家々を回る「門付け(かどづけ)」から夜の境内での「坪舞(つぼまい)」終了まで、また21名が夕方の「堂廻り(どうまわり)」から「坪舞」終了までを体験しました。
「門付け」では、獅子頭を噛み鳴らす「獅子打ち(打ち込み)」も体験させてもらい、学生たちは貴重な経験を得ました。
学生からは、「自分の地元の祭りとは全く違っていた。『門付け』では各家庭のおもてなしがあり、いろいろな方と話ができ、地域のコミュニケーションを楽しく促す大切な行事だと実感できた」、「夜の境内で獅子頭を持って回る役目は、みんなに見られていて緊張したが楽しかった」「獅子が本当に生きているように舞われて迫力があった」などの感想がありました。










地域文化を支える知恵と協力
これまで地域の人たちによって大切に守り、受け継がれてきた祭りや風習などの伝統行事は、担い手不足などの理由により、継続が難しくなってきている現実があります。柳瀬おくんち獅子舞保存会の永松利一会長は「地域の若者が圧倒的に少なく、祭りは存続の危機にある。福岡県の地域伝統行事お助け隊としてボランティア参加してくださる方も連続で来ていただいたり大変助かっている。一度途絶えると、舞い方や祭りの作法や段取りはすぐにわからなくなってしまう。この地域ではすでに面や棕櫚の作り手が途絶えてしまった。そういうこともいろいろな知恵を皆で出し合い、存続できる方法を考えている」と語り、伝統継承の難しさも浮き彫りになりました。
祭りには、福岡県選定保存技術者が生前最後に手掛けたシュロ蓑や、久留米市内の企業が作成した舞い手の衣装など、地域の様々な技術や人々が関わっています。近年では、3Dプリンターの鬼面を久留米リサーチパークなどが支援するなど、新しい技術も取り入れられています。
「普段は別の土地で暮らしているが、おくんちのために帰ってきている。年に1回友達や近所と話をし、舞うのが楽しみ。ここが自分の帰る場所だと感じる」「本来は地域の者で守っていくものだと思うが、大学生や外からの人が支えて盛り上げてくれるのはありがたい。子どもにも残していけるといい」などの声も聞かれました。
学生たちは、伝統文化が地域コミュニティにとってかけがえのないものであり、同時に多くの人々の知恵と努力によって支えられている継承の現場を肌で感じることができました。久留米大学は、これからも地域文化の理解と継承に貢献する活動を推進していきます。